消防のあゆみ
| 年 | 内容 |
|---|---|
| 万治3年 | 甲府市に火消組合が創設された。 これは山梨県における組織的消防の草分けである。火消組合は総町人足600人をもって4組に分けて代官奉行4人を組頭とし、各組の長を設け人足150人をもって編成し、当時の消火は破壊消火と竜吐水であった。 |
| 亨保中 | 甲府町火消が火消人足988人で誕生した。 |
| 延亨中 | 甲府町火消が改組され、各町各主及び組頭が指図し、8町組、3町組、上府中組の3組とし、人足も294人に減じ上鳶、中鳶の2種類編成とした。 |
| 天保中 |
|
| 明治11年3月 | 県令により消防規則が制定され、町火消は5番組制度となり各組は小頭、纏持ち、筒先、刺股、梯子、平夫からなり、全組を統制する頭取、副頭取を置き、腕用ポンプを購入し冷却消火への転換期を迎えた。 |
| 明治27年2月 | 勅令15号をもって消防規則が発令され、甲府市消防組を設け一組四部制に分けた。 各部には組頭1名、子頭3名、消防手30名計133名で編成し、その諸経費はすべて市において負担し、警察の指揮監督のもとに消防活動を行うことになった。 これが公設消防の始まりであった。 |
| 明治30年 |
|
| 昭和3年9月 | 甲府市消防設置規定を交付、市中央部甲府警察署構内に甲府市消防所を設置した。(人員7名) |
| 昭和7年10月 | 市の北部(白木町)、西部(西青沼町)の2ヵ所(共に戦後廃止)に常備消防所の出張所を新設した。(人員16名) |
| 昭和14年1月 | 勅令20号で消防団令が公布され、甲府市消防組を廃止し、甲府市警察団2,568人で結成した。これは戦時下における防空防火の重大な役割を果たした。 |
| 昭和22年4月 |
|
| 昭和22年9月 | 町村合併により西部に貢川出張所(所員6名、ポンプ車1台を配置)を新設した。同27年4月機械化と待遇改善のため人員を整理し、団長以下893名、15分団に再編成した。 |
| 昭和22年12月 | 法律第226号をもって消防組織法が制定公布され、同23年3月施行となり、警察より分離し新制度の消防は完全に市町村の機関となった。 |
| 昭和23年3月 |
|
| 昭和23年7月 | 法律第186号をもって消防法が公布され、9月施行となり消防長以下37名、ポンプ車5台、その他1台をもって甲府市消防本部が開設され、自治体として甲府市消防の面目が一新した。 |
| 昭和23年8月 | 北部に湯村出張所(所員6名、ポンプ車1台を配置)を新設した。 |
| 昭和27年7月 | 消防本部庁舎が落成、盛大な施行式典が行われた。 鉄筋コンクリート2階建、望楼6階建、高さ21.9m延べ面積570㎡。 |
| 昭和29年10月 |
|
| 昭和30年6月 | 北部遠隔地の災害発生時の諸連絡のため、また署配置のポンプ車に機動力をもたすため基地局及び移動局の中短波無線機を設置した。 |
| 昭和30年12月 | 日本損害保険協会から水そう付消防ポンプ車が寄贈された。 |
| 昭和32年12月 | 消防の機動力を強化するため無線付ジープ車2台を新規に配置した。 |
| 昭和33年4月 | 消防団においては、東分団を新設し23分団と陣容を整えた。 |
| 昭和33年5月 | 非常時の人命救助を目的とした救急業務を実施することになり、本署に救急車を配置し、業務を開始した。 |
| 昭和34年12月 | 中継用第1ポンプ車として大型ポンプ車を購入した。 |
| 昭和35年4月 | 本部の組織改革を行い、総務課、警防課、消防署の2課1消防署制を実施した。 |
| 昭和36年1月 |
|
| 昭和36年10月 | 消防体制の確立を図るため消防職員を106名に増員した。 |
| 昭和37年4月 | 急速に進展している東部地域の防火体制完備のため、甲府市消防署東部出張所を新設した。 |
| 昭和38年11月 | 激増する交通事故に対処するため東部出張所に救急車1台を配置した。 |
| 昭和39年4月 | 消防職員を109名に増員した。 |
| 昭和39年12月 | 市南西部に設置してある貢川出張所の改築を行い、防災拠点としての整備を図った。 |
| 昭和40年4月 | 消防職員を112名に増員した。 |
| 昭和40年7月 | 甲府市消防署の組織改革を行い、湯田出張所を消防署に昇格、責任体制を明確化し、2課、2署(丸の内、湯田)制に改革した。 |
| 昭和40年11月 | 科学の発達に伴い複雑多岐にわたる災害に対処するため新鋭化学車1台を購入、丸の内消防署に配置した。 |
| 昭和41年7月 | 湯田消防署管内の救急業務に万全を期するため救急車1台を配置した。 |
| 昭和42年9月 | 甲府市防災対策業務を主管とする防災課を新設し、本部の機構を3課2署制に改革した。 |
| 昭和42年10月 | 本部総務課に火災現場等における指揮命令を迅速かつ適切に周知させるため無線付司令車を配置した。 |
| 昭和43年12月 | 高層建築物災害に対処するため、32m級梯子付消防車を購入、丸の内消防署に配置した。 |
| 昭和45年3月 | 消防職員を116名に増員した。 |
| 昭和45年4月 | 湯田消防署の改革を行い、益々発展しつつある南部の防火体制確立のため、17m級梯子付消防車を配置し、湯田消防署の充実を図った。 |
| 昭和45年8月 | 隣接5ヵ町村の救急業務の委託を受け実施するとともに広域救急体制完備のため、貢川出張所に救急車を配置した。 |
| 昭和45年9月 | 本部警防担当(課)を予防担当(課)に分割独立させ責任体制の確立と予防行政の強力な推進を図った。これにより本部機構を4担当(課)2署制とした。 |
| 昭和45年10月 | 消防署の組織改革を行い、係長制度を採用した。 甲府市消防団の少数精鋭化と処遇改善のため団員の削減を実施し、団長以下1,020名に編成した。 |
| 昭和46年1月 | 甲府市消防団朝日分団を分割して北新分団を新設し、地区分団の整備を図り、24分団に編成した。 |
| 昭和47年4月 | 消防職員を126名に増員した。 |
| 昭和48年4月 | 甲府市ほか5ヵ町村により、甲府地区広域行政事務組合消防本部が発足した。 区域:甲府市、竜王町、敷島町、玉穂村、昭和町、田富町 署所:1本部、2署、3出張所 車両:消防車7台、水そう付消防車2台、化学車1台、梯子 車2台、救急車4台、司令車1台、広報車1台、連絡 車1台作業車1台(甲府市から借用) 職員:122名(甲府市から職員を派遣) 定数:215名 |
| 昭和48年6月 | 消防職員を133名に増員した。 |
| 昭和49年2月 | 消防職員を153名に増員した。 |
| 昭和49年3月 | 消防職員を169名に増員した。 |
| 昭和49年4月 | 消防本部の組織改革を行い、次長制度を採用及び特別救助隊の設置を図るとともに広域消防実働開始に伴い甲府地区内に消防施設、車両及び通信施設を完備し竣工式典が行われた。 署所の新設:西消防署(竜王町)武田出張所(屋形三丁目) 国母団地出張所(昭和町)敷島出張所(敷島 町)田富出張所(田富町)宮本分遣所(御岳町) 車両の購入:消防車5台、水そう付消防車1台、救助工作 車1台、救急車2台、連絡車2台 通信施設の整備:一斉指令装置1台 職員増員:消防職員を181名に増員した。 |
| 昭和49年12月 | 甲府市消防団・竜王町消防団・敷島町消防団・玉穂村消防団・昭和町消防団田富町消防団をもって山梨県消防協会甲府地区支部を結成した。 |
| 昭和50年3月 | 消防本部の増築整備を行い、災害時における防災拠点の庁舎として完成した。 |
| 昭和50年4月 | 消防本部の組織改革を行い、消防行政の積極的な推進を図るため消防相談所を開設した。 消防職員を191名に増員した。 |
| 昭和50年10月 | 高層建築物の人命救助体制確立のため各種救助器具を装備した41m級梯子車を購入、中央消防署に配置した。 中央消防署配置の32m級梯子車は高層建築災害に万全を期するため西消防署に配置した。 |
| 昭和51年3月 | 複雑多様化する災害に対処するため新鋭化学車を1台購入、国母団地出張所へ配置した。 |
| 昭和51年4月 |
|
| 昭和51年11月 | 予防行政の推進を図るため、予防査察車1台を購入した。 |
| 昭和52年1月 | 消防業務の執行体制を強化するため、消防副士長制度を設けた。 |
| 昭和52年4月 | 消防職員を217名に増員した。 |
| 昭和52年10月 | 甲府市消防団千塚分団を分割し、羽黒分団を新設、25分団に編成した。 |
| 昭和53年1月 | 救急業務の推進を図るため新鋭救急車1台及び多数傷病者事故対策のため緊急輸送車1台の寄贈を受けた。 |
| 昭和53年3月 | 水利不足地域の水利確保のため、大型水そう車(10,000㍑)1台を購入中央消防署へ配置した。 |
| 昭和53年4月 | 消防職員を222名に増員した。 組合消防発足5周年記念式典を挙行し、消防本部旗樹立、甲府地区消防の歌を制定した。 |
| 昭和53年11月 | 東部方面の防災拠点として、和戸町に東部出張所の庁舎を新設し移転した。 |
| 昭和53年12月 | 広報業務推進を図るため広報車1台を購入した。 |
| 昭和54年3月 | 救急業務の推進を図るため新鋭救急車1台の寄贈を受けた。 |
| 昭和55年3月 | 中央自動車道西宮線(甲府昭和~韮崎)の救急業務を行うため、新鋭救急車1台を西消防署へ配置した。 |
| 昭和55年4月 | 消防本部の組織改革を行い通信指令室を新設した。 消防職員を230名に増員した。 |
| 昭和56年4月 | 消防職員を240名に増員した。 |
| 昭和56年10月 | 特殊災害対策用として新鋭救助工作車1台を購入し、中央消防署に配置した。 |
| 昭和57年4月 |
|
| 昭和57年10月 | 消防音楽隊規定の一部改正を行い定員26名を33名に増員した。 |
| 昭和58年4月 | 消防職員を256名に増員した。 |
| 昭和58年11月 | 組合消防発足10周年記念式典を挙行した。 |
| 昭和59年3月 |
|
| 昭和59年4月 | 組織改革を行い、消防本部に次長制を、中央消防消防署に副署長ポストを新設、指揮命令系統の改善と事務の効率化を図った。 広報課に音楽隊係を新設した。 消防職員を263名に増員した。 |
| 昭和59年11月 | 災害現場における隊員の安全確保と活動の効率を期するため照明電源車1台を購入し、中央消防署に配置した。 |
| 昭和59年12月 |
|
| 昭和60年4月 | 玉穂村に町制が施行され、玉穂町となる。 消防本部に昭和60年開催される国体リハーサル大会及び61年の本大会の消防警備等の万全を期するために国体消防警備課を新設した。 消防職員定数を274名とし、実員を266名に増員した。 |
| 昭和60年12月 |
|
| 昭和61年3月 |
|
| 昭和61年4月 | 消防署の組織改革を行い、毎日勤務の査察指導係を隔日勤務とし事務の効率化を図った。 消防職員271名に増員した。 |
| 昭和61年8月 | 消防隊員の緊急輸送及び多数傷病者発生事故対策のため、隊員輸送車1台を購入した。 |
| 昭和61年12月 | 第41回国民体育大会及び第22回身体障害者スポーツ大会の終了を併せて国体消防警備課を廃止した。 |
| 昭和61年12月 |
|
| 昭和62年4月 | 消防職員を274名に増員した。 |
| 昭和62年10月 | 西・南各消防署に副署長ポストを新設、指揮命令系統の改善と事務の効率化を図った。 |
| 昭和62年12月 |
|
| 昭和63年4月 | 消防職員の定数を3年増員計画により287名とし、実員を279名に増員した。 |
| 平成元年3月 |
|
| 平成元年4月 | 消防本部の組織改革を行い通信指令室を指令課に改め、広報課を廃止し、総務課内に広報担当を設けた。 消防職員を284名に増員した。 |
| 平成2年3月 | 特殊災害対策用として新鋭救助工作車1台を購入し南消防署に配置した。 |
| 平成2年4月 | 消防本部の組織改革を行い人事教養課を職員課に改め、総務課広報担当を廃止し、指導広報課を新設した。 消防署の組織・業務執行体制の強化を図るため次席制度を廃止し、消防課長制度を導入した。 広域救助活動体制の充実を図るため、中央消防署に特別救助隊(兼務)1隊を配置した。 消防職員を287名に増員した。 |
| 平成3年3月 | 急速に高齢化社会が進展するなかで、災害弱者である65歳以上の一人暮らしの老人の安全を守るため、ふれあいペンダント(緊急通報システム)を設置した。 |
| 平成3年7月 | 救急業務の推進を図るため、新鋭救急車1台の寄贈を受けた。 |
| 平成4年4月 | 消防本部の組織・業務執行体制の強化を図るため、次長制度を廃止し、副消防長制度を導入した。 |
| 平成5年4月 | 組織改革を行い、職員課を人事課に、指導広報課を広報課に改め、予防課に査察係を新設した。 消防署の隔日勤務の予防係を毎日の勤務に、毎日勤務の庶務係を隔日勤務とし、事務の効率化を図った。 中央消防署の特別救助隊に専任の隊長を配置し、広域救助体制の強化を図った。 |
| 平成6年2月 | 高規格救急自動車の運用を開始した。 |
| 平成6年4月 | 消防職員の定数を3年増員計画により305名とし、実員を295名に増員した。 消防署の予防及び査察事務執行体制の充実強化を図るため、予防課長制度を導入するとともに、隔日勤務の査察指導係を毎日勤務とした。 |
| 平成7年1月 | 在宅の一人暮らし老人のためのふれあいペンダント(緊急通報システム)に、新たに在宅の一人暮らしの重度身体障害者の安全を確保するための在宅障害者緊急通報システムを加えた。 |
| 平成7年3月 | 高規格救急自動車1台の寄贈を受け、中央消防署に配置した。 |
| 平成7年4月 |
|
| 平成8年3月 |
|
| 平成8年4月 | 消防職員を305名に増員した。 平成8年開催される高校総体の消防警備等の万全を期するために警防課に高校総体係を新設した。 |
| 平成8年12月 | 大規模災害時等の偵察・情報収集活動などを行うため、震災用オートバイ3台を購入し、3署に配置した。 |
| 平成9年2月 | 署所の配置の適正化を図るため、中央消防署を移設した。 |
| 平成9年3月 |
|
| 平成9年4月 | 消防職員の教育研修体制の充実強化を図るため、人事課教養係を人事課教育研修係に改めた。 消防署の組織の業務執行体制の円滑化を図るため、課長制度を廃止し、次席制度を導入した。 救急業務執行体制の強化、効率化を図るため、3出張所に救急隊長を設けた。 高校総体の終了に伴い、警防課高校総体係を廃止した。 |
| 平成10年2月 | 緊急消防援助隊の救急部隊として災害対応救急自動車及び高度救急処置用資機材を購入し、西消防署に配置した。 |
| 平成10年3月 |
|
| 平成11年3月 | 緊急消防援助隊の後方支援部隊として支援車及び援助隊支援資機材等を購入し、消防本部に配置した。 消防本部の車庫兼倉庫を新築した。 |
| 平成11年5月 | 21世紀を目前にした地方分権、行財政改革等の推進と高度情報化から環境問題に至る諸問題に的確に対応するため、消防行政の2本柱である予防、警防業務の責任体制を明確化し、「消防次席」を「警防次席」とし、さらに一般行政と整合を図るため「専門主任」を「主査」とした。 予防行政においては、複雑多様化する防火対象物の査察執行の実を上げるため消防本部予防課「査察係」を「査察指導係」とし、署の「査察指導係」を「査察係」とした。 また、救急救命需要の増加に伴い、的確な救命処置指導を行えるよう、指令課に救急救命士を配置した。 |
| 平成12年4月 | 消防本部及び消防署の責任体制を明確化するため副消防長制度を廃止し本部統括及び署統括の2次長制度を導入した。 企画調整部門の強化格付けを図るため本部に主幹を設置した。 救急業務の高度化等に的確に対応し防火防災意識の積極的な推進を図るため防災救急課を設置した。 火災原因究明の迅速的確な処理をするため、調査係に第一係、第二係を設置した。 |
| 平成13年4月 | 本部及び署統括次長の兼務を解き、独立させ責任体制をより明確化し、指揮命令系統を充実させた。 主幹を企画主幹とし、企画調整部門等消防長の指定する事務を担当するなど組織の強化を図った。 各署の警防係長の下に主査を配置し、警防体制の強化を図った。 また、救急要請時において的確な処置指導に対応するため指令課に救急救命士を増員した。 |
| 平成14年2月 | 昭和出張所及び玉穂出張所へ救急車を配置した。 |
| 平成14年4月 | 消防本部情報ネットワークが構築され、財務会計システム及びグループウェアの運用開始により、事務の効率化が図られ、経理係と管財係を統合し「財務係」に改め、人員の削減が図られた。 また、適正な情報管理等を推進するため、「企画係」を新設し、グループウェアを最大限に業務に反映させ、効率的な業務が遂行できるようになった。 |
| 平成14年11月 |
|
| 平成14年12月 | 中央消防署の救助工作車を更新した。 |
| 平成15年4月 | 効率的かつ能動的な業務遂行が出来るよう企画主幹、企画係長を総務課に配置し、企画事務の強化を図った。 消防総合情報管理のシステムの構築に伴い指令課に情報管理係を新設した。 南消防署特別救助隊に副隊長を配置し広域救助体制の強化を図った。 |
| 平成15年9月 |
|
| 平成15年10月 |
|
| 平成15年12月 | 南消防署田富出張所の高規格救急車を更新した。 |
| 平成16年1月 |
|
| 平成16年4月 | 平成15年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練の終了に伴い緊急消防援助隊係を廃止した。 消防業務の総合的企画部門の必要性から企画主幹ポストを企画課に昇格し新設した。 新設に伴い指令課情報管理係を企画係に統合し、消防総合情報管理システム構築の一元化を図った。 |
| 平成16年9月 | 中巨摩郡竜王町、同敷島町及び北巨摩郡双葉町の3町合併により「甲斐市」となる。 |
| 平成17年2月 | 西消防署の高規格救急車を更新した。 |
| 平成17年3月 | 複雑多様化する災害対応するため最新鋭のコンピュータと最新の通信機器を駆使して「高機能消防指令センター」を整備した。 西消防署庁舎の耐震化工事と訓練棟を整備した。 |
| 平成17年4月 | 消防本部の組織改革を行い総務課に主幹を配置し、組織構成市町の配置分合に伴う広域消防のあり方、消防救急無線のデジタル化等調査研究を担当し、防災救急課を廃止して、救急救助係を警防課に移設、防災広報係を査察指導係に統合し、また、各消防署に調査係を配置した。 |
| 平成17年12月 | 南消防署の高規格救急車を更新した。 |
| 平成18年1月 | (社)日本損害保険協会から高規格救急車の寄贈をうけ、中央消防署東部出張所に配置した。 |
| 平成18年2月 | 中巨摩郡玉穂町、同田富町及び東八代郡豊富村の3町村合併により「中央市」となる。 |
| 平成18年3月 | 東八代郡中道町及び西八代郡上九一色村の北部(梯、古関地区)が甲府市へ編入合併した。 |
| 平成18年4月 | 中道出張所(所員8名、水槽付ポンプ車1台、高規格救急車1台)を開設、消防職員を実員309名に増員した。 |
| 平成18年12月 | 片川昇氏から高規格救急車の寄贈を受けた。 |
| 平成19年1月 |
|
| 平成19年2月 | 中央消防署開署式を挙行した。 |
| 平成19年4月 | 消防職員を実員316名に増員した。 |
| 平成19年5月 | 高部正男消防庁長官が地方消防行政視察のため来庁した。 |
| 平成20年4月 | 高度救助隊(隊員16名)を南消防署に配置した。消防職員を実員321名に増員した。 |
| 平成21年4月 | 消防広域化推進計画(H20.5県)の策定に伴ない、広域化担当として企画課に主幹を設置した。消防職員を実員324に増員した。 |
| 平成22年1月 | 南消防署に仮設訓練塔を設置した。 |
| 平成22年2月 | 西消防署に配置している高所作業車を更新した。(名称を屈折はしご車に改めた。) |
| 平成22年3月 | 南消防署中道出張所の高規格救急車を更新するとともに、消防指導支援用として防災指導車を購入した。 |
| 平成22年4月 | 南消防署昭和出張所の救急隊を選任救急隊とした。消防職員を実員326名に増員した。 |
| 平成22年9月 | 中央消防署に仮設訓練塔を設置した。 |
| 平成22年12月 | 高圧ガス製造事業所が完成した。(南消防署昭和出張所敷地内) |
| 平成23年2月 | 中央消防署武田出張所・湯村出張所の普通ポンプ車を災害対応特殊消防ポンプ車に更新した。 |
| 平成23年12月 | 南消防署に配置しているはしご車(1台)を更新した。 |
| 平成24年4月 | 予防課の査察指導係と広報係を統合し査察指導・広報係とした。 消防職員を実員329名に増員した。 |
| 平成25年2月 | 中央消防署・南消防署に水槽車を配置した。 |
| 平成25年3月 | 中央消防署湯村出張所に作業車(1台)、南消防署にBC災害資機材搬送車(1台)を更新した。(名称をそれぞれ林野火災工作車、特殊災害用資機材搬送車に改めた。) |
| 平成25年4月 | 消防救急無線のデジタル化整備等に伴い、指令課にデジタル化推進係を設置した。消防職員を実員331名に増員した。 |
| 平成26年1月 | 南消防署玉穂出張所・西署に配置している高規格救急車(各1台)を更新した。 |
| 平成26年3月 | 南消防署に配置している救助工作車を更新した。 消防救急無線のデジタル化及び高機能指令センターを改修した。 |
| 平成26年4月 | 指令課デジタル化推進係を廃止した。 事務の効率化及びスリム化を図るため、総務課の財務係と装備係を統合「財務係」とし、人事課の人事係と職員係を統合し「人事係」とした。 |
| 平成27年4月 | 「査察指導・広報係」の広報業務を企画課企画係に移管「査察指導係とし、「企画課企画係」を「企画課企画広報係」とした。 |
| 平成28年4月 |
違反対象物に係る公表制度実施のため体制を整備し、違反是正を強化するため、予防課に「違反是正係」を新設した。 警防課の「調査係」を廃止した。 |
| 平成29年1月 | 中央消防署東部出張所・南消防署中道出張所に配置している普通ポンプ車(各1台)を更新した。 |
| 平成29年3月 | 中央消防消防署に配置しているはしご車(1台)を更新した。 |
| 平成29年4月 | 救急及び救助の専門化・高度化、緊急消防援助隊の体制強化及び訓練指導等の体制の充実強化を図るため、「救急救助課」を新設した。 |
| 平成29年9月 | 総務省消防庁より燃料補給車が無償貸与され、消防本部に配置した。 |
| 平成29年11月 | 西消防署に配置している屈折はしご車の初期の機能及び安全性を確保するため艤装部分をオーバーホールした。 西消防署敷島出張所に配置している高規格救急車を更新した。 |
| 平成30年3月 | 西消防署に配置している救助工作車を更新した。 |
| 平成30年9月 | 南消防署に配置しているはしご車の初期の機能及び安全性を確保するため艤装部分をオーバーホールした。 |
| 平成31年2月 | 西消防署貢川出張所に配置している普通ポンプ車、中央消防署及び南消防署に配置している高規格救急車(各1台)を更新した。 |
| 平成31年4月 | 効率的な業務推進のため、企画課を総務課に統合し、「企画調整主幹」及び「情報・広報係」を新設した。 |
| 令和 2年2月 | 昭和出張所に配置している高規格救急車(1台)を更新した。 |
| 令和 2年3月 | 西消防署に配置している化学車(1台)を更新した。 |
| 令和 2年7月 | 女性消防吏員の活躍及び募集等を題材に本部予防査察車(1台)にラッピングを施した。 |
| 令和 2年11月 | 消防本部に配置している支援車(1台)を更新した。 |
| 令和 3年3月 | 中央消防署に配置している水槽付ポンプ車(1台)を更新した。 |
| 令和 4年1月 | 一般財団法人救急振興財団より救急普及啓発広報車が寄贈され、消防本部に配置した。 |
| 令和 4年3月 | 消防本部に配置している資機材搬送車及び昭和出張所に配置している普通ポンプ車(各1台)を更新した。 |
| 令和 4年4月 | 指揮・命令系統を明確化し、大規模災害等発生時等の対応力を強化するため、「本部次長」の職名を「副消防長」に変更した。一体的な行財政運営の構築を図るため、総務課に配置された「企画調整主幹」及び「財務係」の財政業務を統合し、「企画財政課」を新設した。また総務課に管財業務及び情報広報を所管する「行政経営係」を新設した。違反是正及び査察執行体制を強化するため、予防課の「査察企画係」及び「違反是正係」を分離し、「査察課」を新設した。 |
| 令和 5年3月 | 西消防署・南消防署中道出張所に配置している高規格救急車(各1台)を更新した。 |
| 令和 5年4月 | 甲府地区広域行政事務組合職員定数条例(消防職員)を335名から371名に改めた。予防業務の窓口を一元化し、利用者の利便性の向上、複雑多様化する防火対象物への対応能力の向上及び人員の効率化を図るため、「予防課予防係」及び「各消防署予防係」を統合し、「予防課予防審査係」を新設した。総務部門の効率化を図るため、各消防署庶務係の勤務形態を隔日勤務から毎日勤務に変更するとともに、各消防署査察係と併せて庶務係を所管することから、各消防署「予防次席」を「総務統括」に変更した。当直責任者であることを明確にしつつ、指揮命令系統の一層の強化を図るため各消防署「警防次席」を「当直統括」に変更した。 |

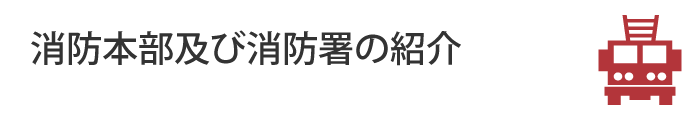
 町火消初代組頭に内藤岩吉がなり、半纏を作り、統制ある町火消として甲府の守護に任じた。
町火消初代組頭に内藤岩吉がなり、半纏を作り、統制ある町火消として甲府の守護に任じた。 時代の推移に伴う市民の要望と、消防幹部の努力により「常備消防部」が創設され、蒸気ポンプと機関士ほか1名を常置した。
時代の推移に伴う市民の要望と、消防幹部の努力により「常備消防部」が創設され、蒸気ポンプと機関士ほか1名を常置した。 勅令をもって消防団令が公布され、翌23年消防団条例を制定、団長以下1,702名をもって改組した。
勅令をもって消防団令が公布され、翌23年消防団条例を制定、団長以下1,702名をもって改組した。 南部に湯田出張所(所員6名、ポンプ車1台を配置)を新設した。
南部に湯田出張所(所員6名、ポンプ車1台を配置)を新設した。 町村合併促進法によって隣接10ヵ村の編入合併により、消防団においては7分団を加え一躍22分団1,397名、機械力も三輪車4台及び可搬動力ポンプ11台を増置した。
町村合併促進法によって隣接10ヵ村の編入合併により、消防団においては7分団を加え一躍22分団1,397名、機械力も三輪車4台及び可搬動力ポンプ11台を増置した。 高層建築物の火災防ぎょ、人命救助に万全を期するため17m級梯子付消防車を1台購入した。
高層建築物の火災防ぎょ、人命救助に万全を期するため17m級梯子付消防車を1台購入した。 消防本部の組織改革を行い、次長制度を廃止、広報課を新設した。 消防音楽隊規定を制定し、隊長以下19名を以って発足した。 消防職員を206名に増員した。
消防本部の組織改革を行い、次長制度を廃止、広報課を新設した。 消防音楽隊規定を制定し、隊長以下19名を以って発足した。 消防職員を206名に増員した。 消防本部の組織改革を行い人事教養課を新設し、中央消防署宮本分遣所を出張所に昇格した。 消防職員を248名に増員した。
消防本部の組織改革を行い人事教養課を新設し、中央消防署宮本分遣所を出張所に昇格した。 消防職員を248名に増員した。 市街化が進む西部方面の防災拠点の整備を図るため、貢川出張所の新築を行った。
市街化が進む西部方面の防災拠点の整備を図るため、貢川出張所の新築を行った。 広域南部の消防力の強化充実を図るため、玉穂村に南消防署玉穂出張所を新設、消防車1台を配置した。
広域南部の消防力の強化充実を図るため、玉穂村に南消防署玉穂出張所を新設、消防車1台を配置した。 広域南西部の消防力の強化充実を図るため、国母団地出張所を昭和町に移転新築し、南消防署昭和出張所とした。
広域南西部の消防力の強化充実を図るため、国母団地出張所を昭和町に移転新築し、南消防署昭和出張所とした。 高層ビル災害に備えて、新鋭高所作業用消防車SAスカイアームΣ16を購入し、中央消防署に配置した。
高層ビル災害に備えて、新鋭高所作業用消防車SAスカイアームΣ16を購入し、中央消防署に配置した。 広域北西部の防災拠点の整備を図るため、中央消防署湯村出張所の移転新設を行った。
広域北西部の防災拠点の整備を図るため、中央消防署湯村出張所の移転新設を行った。 西消防署に配置の30m級梯子車を4輪操舵、傾斜きょう正装置付新鋭梯子車に更新した。
西消防署に配置の30m級梯子車を4輪操舵、傾斜きょう正装置付新鋭梯子車に更新した。 消防防災拠点の整備を図るため伊勢三丁目地内に消防本部及び南消防署を新築移転した。 複雑、多様化する各種災害に迅速かつ的確に対応するため通信指令室に消防緊急情報システムを導入した。
消防防災拠点の整備を図るため伊勢三丁目地内に消防本部及び南消防署を新築移転した。 複雑、多様化する各種災害に迅速かつ的確に対応するため通信指令室に消防緊急情報システムを導入した。 消防職員を301名に増員した。 広域南西部の消防力の強化充実を図るため、南消防署田富出張所の移転新築を行った。
消防職員を301名に増員した。 広域南西部の消防力の強化充実を図るため、南消防署田富出張所の移転新築を行った。 中央消防署に配置の40m級梯子車を4輪操舵、傾斜きょう正装置付新鋭梯子車に更新した。
中央消防署に配置の40m級梯子車を4輪操舵、傾斜きょう正装置付新鋭梯子車に更新した。 大規模災害対策用として、救助工作車Ⅲ型を購入し、南消防署に配置した。 複雑多様化する特殊災害対策用として化学消防車Ⅱ型を購入し、中央消防署に配置した。
大規模災害対策用として、救助工作車Ⅲ型を購入し、南消防署に配置した。 複雑多様化する特殊災害対策用として化学消防車Ⅱ型を購入し、中央消防署に配置した。 西消防署敷島出張所を移転新築した。
西消防署敷島出張所を移転新築した。 西消防署敷島出張所の救急車を高規格救急車に更新し配置した。
西消防署敷島出張所の救急車を高規格救急車に更新し配置した。 甲府地区消防本部ホームページを開設した。
甲府地区消防本部ホームページを開設した。 平成15年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練が、山梨県小瀬スポーツ公園を主会場に関東ブロック1都9県、80消防本部、9航空隊、678名の隊員が参加し実施された。
平成15年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練が、山梨県小瀬スポーツ公園を主会場に関東ブロック1都9県、80消防本部、9航空隊、678名の隊員が参加し実施された。 水槽付ポンプ車を購入し中央消防署に配置した。
水槽付ポンプ車を購入し中央消防署に配置した。 電源照明車を更新した。(南消防署配置)
電源照明車を更新した。(南消防署配置)